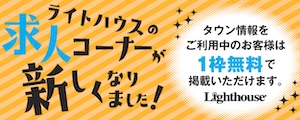|
「好きだから一生懸命やる」を貫きアートディレクターに
高校まで野球一辺倒。絵を描き始めたのは、卒業後に留学した短大のクラスが 初めてだったと言う堤さん。好きになったら熱くなり、とことん打ち込む性格だ。『Toy Story 3』のアートディレクターを務めるまでになった、その経緯を聞いた。
【堤 大介さんのプロフィール】
つつみ・だいすけ◎1974年、東京生まれ。高校まで硬式野球に打ち込み、卒業後、ニューヨーク州のRockland Community Collegeに留学。同大在学中、イラストレーションに開眼した。ニューヨーク市にあるSchool of Visual Artsに奨学金生として編入し、首席で卒業。Lucas Arts Entertainment Companyに勤務後、Blue Sky Studioに転職。その間に、『Ice Age』『Robots』『Horton Hears A Who』のコンセプトアートを担当。2006年、『Toy Story3』のアートディレクターとしてPIXARに移籍する。
高校に打ち込んだ経験で努力を厭わない体質に

才能あふれるクリエーターたちをまとめていくのがアートディレクターの仕事 ©PIXAR ANIMATION STUDIOS
|
僕は18歳まで野球をやっていました。体格に恵まれていたら、プロになりたかったくらい好きで。今もサンフランシスコ・ベイエリアの日本人の硬式野球チームで、選手兼監督をやっています。アニメーションの世界でここまで頑張れたっていうのは、野球に真剣に打ち込んできたから。高校時代のチームは、施設も整っていないし、有力選手も全然集まらないから、どんなに頑張っても勝てる訳がありませんでした。勝利という見返りがなくても努力し続けるっていうのは、難しいことだと思うんです。でも、僕は野球が本当に好きだから、一生懸命やるのが苦じゃなかった。
野球のやり過ぎで、受験戦線から早々に脱落(笑)。母親が「18を過ぎたら親元を離れ、違う街に行きなさい」と言っていましたから、浪人するという選択肢はありませんでした。姉がアメリカに留学していたから、僕もとにかく留学して、何か見つけようと思いました。
ニューヨークの小さなコミュニティーカレッジに入って、英語ができないからESLを取っていました。英語力があまりなくても取れるクラスのうちの1つが、絵のクラスでした。それが絵を描き始めたきっかけです。クラスメートは、おじいちゃんやおばあちゃんばかりで優しいから、僕の描いた絵を無条件ですごく褒めてくれた。それで自分は才能があると思っちゃって、真剣に絵を描き始めたんです。
日本という国は、食にしても建築にしても芸術にしても歴史があり、深いものがあります。日本人のちょっとしたこだわりや、細部に対する美意識って、世界的に見るとアドバンテージなんですね。僕は、日本の古典美術は勉強していないんですが、日本独自の、日本で過ごして育まれる平面的な物の見方が、自分の中にあるのかなって感じます。
好きなイラストレーションにひたすら没頭した美大時代

堤さんによる『Toy Story 3』のコンセプトアート ©PIXAR ANIMATION STUDIOS
|
4年制の大学でも引き続き絵をやりたいと思って、それなら美大に編入しようと思いました。ただ、美大は私立が多く、その高額な学費を払う余裕はありませんでした。ですが、School of Visual Artsというマンハッタンにある私立の美大から奨学金がもらえることになったんです。編入後、1教科でも成績B以下になったら奨学金の支給が止まるので、必死で頑張りました。と言っても、好きなイラストレーションを専攻していたので、全然辛くはなかったんですが。マンハッタンでいっぱい誘惑はあったんですが、不思議なくらい遊びに出かけることはなかったです。それ以上に絵の勉強が楽しかったんですね。
僕が絵を描き始めたのは留学してからなので、周りには僕より上手い人はいっぱいいました。それでも腐らないで描き続けられたのは、野球をやっていた時と同じ「好きなんだから、やりたい」っていう気持ち。もし、そこで折り合いを付けて無難な道を選んでいたら、人生は変わっていました。
3年生の時に、ディズニー主催で1カ月間のトレーニングコースみたいな夏のキャンプがあり、それに参加できました。これが僕の意識を変えました。アメリカとカナダの美大から35人だけが選抜されるのですが、僕は36番目。ですが運良く1人欠員が出て、参加できることになったんです。参加してみて、講師のディズニーの人たちの絵が本当に素晴らしかったんです。その時、僕もディズニーで働けば、上手くなれるのかなって期待感が生まれたんですよ。
美大を首席で卒業したのですが、当時は2Dのディズニーのアニメーションが衰退し始めた時代で、ディズニーは誰も雇っていませんでした。そこで、サンフランシスコの近くにあったジョージ・ルーカスのビデオゲーム会社に雇ってもらい、そこで2年間働かせてもらいました。
僕と同じように絵が大好きで、しかも絵が上手な人たちがいて、その人たちとコラボレーションするのが楽しくて仕方がなかった。ただ、僕はビデオゲームをしないので、どうしてもゲームを作ることに違和感がありました。
やはり映画の仕事がしたいということで、ニューヨークにあったBlue Sky Studioという映画会社に転職しました。そこで初めて映画のイロハを全部学んで、『Ice Age』『Robots』『Horton Hears A Who』の3本でコンセプトアートを担当しました。脚本がまだ絵になっていない段階で、イラストレーターが絵を描いて、「こういう感じでいきましょう」という案を出していくのがコンセプトアーティストの仕事。ストーリーを伝える絵を描くのが好きだったので、これは天職でした。
Blue Sky Studioでは、7年働いたのですが、その間、PIXARから何度か誘いを受けていました。ただ、その都度PIXARが僕にやってほしい仕事と僕がやりたいと思っていた仕事が違っていたので実現しませんでした。転職が実現したきっかけは、リー・アンクリッチ監督が、僕の個人サイトからEメールで、『Toy Story 3』でアートディレクションをやってほしいとオファーしてきたことでした。今から4年前のことです。
アンクリッチ監督による『Toy Story 3』は、映像的にもストーリー的にもダークです。1と2を監督したジョン・ラセター監督は常にカラフルで、夜のシーンでもできるだけ光を入れるような人。それと比較すると、アンクリッチ監督は子供向けの映画からちょっと外れた感覚を持っています。僕はずっと子供用のアニメーションをやってきましたが、結構ダークな絵も描いています。多分そういうところが監督に響いたのだと思います。
200人の頑固職人をまとめ上げる手腕
『Toy Story 3』の仕事は、200人のチームで取り組みましたから、チームワークがすごく大切。ずっと野球をやっていましたので、協調性を身に付けていました。そして、アートディレクターとして大切なことは、コミュニケーション能力です。監督が言わんとしていることを察すること。これは、日本で生まれ育ち、自然と「言わずとも察する力」を持っていて助かりました。コンセプトアートを見せて、「これは違う」と言われることはしょっちゅうです。違うと言われて、次に見せる物が少しでも監督の要望に近付いていないといけない。僕は、監督の求めている映像にできるだけ近付けるよう手助けするミニ監督みたいなものです。
アートディレクターは、最初に監督と直接やり取りできる数少ない人間です。その後、実際にアニメーションを作る大勢の人たちに、「この絵を基に、これを作ってください」と指示を出すことになります。例えば、僕は色とライティングのアートディレクターでしたから、映画を通して、それらに統一性を持たせないといけなかった。ですが、ただ単に「こうしてください」と指示を出しても、皆すごい才能のあるアーティストたちだから、職人気質で簡単には聞いてくれない(苦笑)。僕の言うことよりも、自分のやりたいようにやりたいという人もいます。それをうまくなだめすかして、僕の指示ではなく、あたかも自分の意志でやっているかのように、仕事をさせるよう仕向けないといけないんです。
あとは、もちろん絵のクオリティーですね。彼らが僕の絵を見て、こんな素晴らしい映像を作りたいと思ってくれるかどうか。絵も含めてコミュニケーションなんです。僕はPIXARの生え抜きではない、外様の新入りアートディレクターでしたから、なおさら口で言うよりも、自分の絵で納得してもらうしかないんです。
アンクリッチ監督は、『Toy Story 3』ができあがった時にTVのインタビューで、PIXARで1回も働いたことがない外部の人間を、いきなりアートディレクターに雇うということは大変なリスクがあったし、社内で反対もされたと話していました。しかも、彼にとってもこの映画は初めてのソロ監督作品でした。だから、できれば周りは経験豊富な人で固めたいはずでした。でも、そのリスクを負ったおかげで、こういう作品ができて良かったと言ってくれました。
「人の心に残る良い作品を作るのが喜び」(堤さん)
『Toy Story 3』は、大勢の才能あふれるクリエイターたちが、力を合わせたからできたんです。あの感動は1人では絶対に作れません。自分の絵を元に作られた映像が、他の才能が加わることでさらに洗練され、すごいものになった時の充実感はたまらないです。「自分も作品に貢献したし、大勢の人たちにも貢献する場を与えられた」と、うれしく思います。自分一人だけで絵を描いていても、多分そこまでの満足感は得られないでしょう。
僕が思う良い作品っていうのは、見ている人に何かを伝えようとする意思がある作品だと思います。見ている人たちの心に残る作品と、その場でただ笑って終わりという作品は雲泥の差なんですね。人の心に残るものを作るって、やっぱり難しい。そんな手間をかけるくらいだったら、エンターテインメントにこだわって、笑わせるものだけ作ればいいというのが、無難なビジネスモデルです。
その中でPIXARは、業界人以外が見ても良いと感じる映画を作っています。心に残る作品を作るという明確な意思があるんですね。もちろん、それが空回りすることもあるでしょうが、結果的にどうというより、作り手がそれを大事に思っているかどうかが大切。
作り手側からしてみれば、興行収入ってあまり関係ないんです。良い作品が作れなければ、やはり全然面白くないんですね。僕は最終的な映像・作品が、自分の求めているもの、自分の思っていたのと全然違うというのは納得いかないんですよ。だって映画を作るために絵を描いている訳ですから。PIXARは、経営陣のクリエイターへのリスペクトが感じられるのでうれしいです。
世の中にはすごい人たちがいっぱいいて、そういう人たちを見ていると、自分はまだ本当に駆け出しだと感じます。学ぶことは、自分の部下も含めていっぱいあります。今の立場に安住して、堤=この絵/この色、みたいに定着してしまうのは危険なんですよ。自分は枠に入りたくないので…。
そして、いつかは、自分のオリジナルのメッセージを伝えていきたいですね。
(2011年1月1日号掲載)