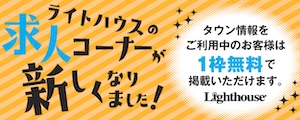|
ジビエとはなんぞや。
漢字だと「地冷え」? それとも「痔冷え」かな? さもなきゃ「耳鼻江」っていう女性のなまえ?
日本語だとなんとも重々しいサウンドだが、じつはこれはフランス語で「gibier」。猟の獲物のことである。英語でいえば「game」だ。
これから秋が深まって、冬になるとその季節となる。
フランスをはじめヨーロッパの食道楽たちは、それが楽しみで、いまごろからわくわくしてくるのである。
なぜ楽しみにするかというと、秋から冬に、森に入って「狩り」というスポーツを楽しむのが、ヨーロッパの上流階級の伝統であるということがひとつ。
食べる側からいっても、季節の食べものを楽しむというのは、日本でも秋の味覚マツタケとか冬のニシンとかを楽しむのと同じ感覚である。
では、なぜ狩りの獲物は秋から冬がうまいのだろう?
それは、野山の鳥獣は、冬になるまえにたくさん食べものを食べて、栄養や脂肪を体に蓄積させるからである。
せっかく一所懸命蓄積したところを人間に獲られてしまうのはちょっとかわいそうだが、そこはカンベンしてもらって食べてみよう。
秋から冬になると、パリのレストランでもジビエをメニューにのせる店がでてくるし、郊外の店にいくと、もっとよくお目にかかる。
英語でいえば、鳥関係がwild duck(野ガモ)、grouse(雷鳥)、partridge(ヤマウズラ)、snipe(シギ)、teal(コガモ)、woodcock(ヤマシギ)、pheasant(キジ)など。
venison(シカ類)もいろいろあるが、roedeer(ノロジカ)がいちばんうまいとされている。
hare(ウサギ)やboar(イノシシ)もある。
養殖でない天然のシャケやマスも、彼らにとってはジビエの一種だ。
ほかにももっと、ジビエがよろこばれる理由がある。
それは味だ。
じっさいに、人間に育てられた動物や鳥と、野生のものでは、まったく別物といっていいほど味がちがう。
日本の食通たちも、たとえば養殖のはまちと天然のはまちはまったく別物だとよくいうが、それと同じこと。
たとえばカモ。
当然といえば当然だが、野生には強烈な野生臭さがある。
英語では「earthy」と表現される土臭さ、森の匂い、あるいはキノコに似た香り、それらがなんともいえないうまさ、他のいかなる食べものともちがうパワーをうみ出している。
はじめて食べたひとはムッとくるかもしれない。
しかし、それが慣れたひとにはコタエられないものとなる。
農場ではホルモンや抗生物質を与えたり、脂肪の多い食餌を与えて、運動不足にさせて太らせて利益をあげようとするわけだが、野生のカモは空を飛びまわり、沼の虫や魚をみつけて食べていたわけだから、
比較にならないほど脂肪が少なく身がひきしまっている。
つまり、骨ばっている。肉の部分がずっと少なく、肉の骨離れがわるく、簡単にいえば食べにくい。
でもそれが野生のうまさの証拠なのである。
コレステロールも少なく、蛋白質が高く、繊維質が多いらしい。
そういう意味でも健康的なわけだ。
そして、もうひとつ食道楽がよろこぶ理由が、一匹一匹、一羽一羽の味がちがうことだ。
管理された大量生産のものとはちがい、食べてみるまで味や香りの予測がつかない楽しさがある。
この一羽の鳥が、どんなものをどれだけ食べて生きてきたんだろう、どれだけ空を飛んだのかなあ、と食べながら想像するのも楽しいものだ(食べられてるほうはおおきなお世話だろうが)。
料理方法は、丸ごとスモークしたりグリルして、フルーツのソース、あるいはミントやクレソンなどの香草も適宜使って、味のバランスのいい料理にしあげるのが料理人の腕のみせどころでもある。
ただし、ジビエには鉄砲のタマが入っていることがあるので注意してください(ホントです。僕も経験があります)。
(2005年11月16日号掲載)