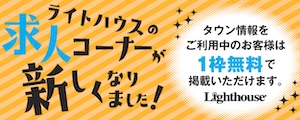自分のルーツは”資産”。誇りを持った時、道が開ける。
世界の恵まれない子どもたちに絵本を制作&寄贈するプロジェクトを立ち上げ、支援を続けている画家、藤田理麻さん。チベットのダライ・ラマ法王との交流もある藤田さんが社会活動に目覚めた経緯と、これまでの活動について伺いました。
(2017年7月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版掲載)

ふじたりま◎東京都生まれ、兵庫県芦屋育ち。NYの名門、パーソンズ・スクール・オブ・デザイン在学中に画家デビュー以来、雑誌や広告で引っ張りだこに。南カリフォルニア、NY、東京、インドを行き来し、各地で個展を開催。Web: http://rimafujita.com
|
―画家になった経緯を教えてください。
藤田理麻さん(以下、藤田理麻):一人っ子だったこともあり、子どもの時から一人でお絵描きをして遊ぶことが多かったんです。中学生の時に父親の仕事の関係でNYに引っ越した後も、いつも校内で絵を描いていました。両親が帰国する時、「アーティストを目指すなら、アメリカがいいかもしれない。残ってもいいよ」と言ってくれ、デザイン界で有名なパーソンズ・スクール・オブ・デザインに進学。ありがたいことに在学中から絵が売れて、画家としてデビューしました。
―アメリカに来たことは作品にどう影響していますか?
藤田理麻:渡米して最初に通った学校は生徒の99%がマンハッタンの大富豪の子どもという特殊な環境でした。友だちがほしくて彼・彼女らに近付こうとしましたが、相手にしてもらえませんでした。ある日、人気グループの男の子が突然「歌舞伎役者にはどうして男性しかいないの?」と聞いてきました。「知らない」と答えたら、「日本人なのに日本のことを知らないんだね」と。その時、はっとしました。私は日本人なんだから、誇りを持って日本人らしくしていればいいんだって。そうして自分の態度が変わったら、面白いように友だちが増えました。
以来、「自分のルーツは資産」が私のモットー。絵を描く時に日本人らしさや日本らしさを常に意識しているわけではないですが、私にしか描けない絵を描けばいいという気持ちは絵に影響していると思います。
―独特の世界観のある絵の構想はどこから得るのですか?
藤田理麻:目で見えるものを描いていた時代もあるのですが、今は夢で見たビジョンを描いています。不思議と、細部まで全部覚えているんです。だから、絵について「なぜこう描いたの?」と聞かれても答えられません(笑)。注文をいただいて描く場合も、夢でイメージが降りてくるまで待たせていただきます。絶対に出てくるんです。必要なことは、自分をピュアに保つこと。そのためにメディテーションを日課にしています。
―恵まれない子どもたちを絵本で支援するプロジェクト
「ブックス・フォー・チルドレンBFC)」を始めたきっかけは?
藤田理麻:BFCの立ち上げは2001年ですが、その発端となった出来事は1993年頃、JFK空港で起こりました。高熱でぼんやりしていた私はドル札を全く持っていなくてタクシーに乗りたいのに乗れない…すると目の前に突然、女性が現れてお金を握らせてくれ、あっという間に姿を消しました。それからしばらくして行った本屋で、目の前の棚から一冊の本が落ちてきました。見知らぬ誰かに助けられた体験談を集めた本でした。その時、JFK空港でのことが蘇り、「人生の目的とは利他主義だ!」と思いました。それまでキャリアは順調でしたが、幸せではなかったんですね。この時から、絵は目的ではなく、誰かのために役立てる手段なのだと意識が変わったんです。

藤田さんの絵本によるチベット難民孤児支援の取り組みを、ダライ・ラマ法王が賞賛。
|
―特にチベットの難民孤児支援に力を注いでいるのはなぜ?
藤田理麻:ちょうど同じ頃、夢で「チベットのために今すぐ何かをしなさい」という強い声を聞きました。とにかく何かしようとまずは関連団体でボランティアを始めました。そのうち、チベット人の友だちができて、話をしているうちに「私は画家だから絵本なら作れる!」とひらめきました。
中国に侵攻されたチベットではチベット語を学べず、文化も消えていっています。私のモットーは「自分のルーツは資産」ですから、チベットの民謡の絵本をチベット語で作ってチベット難民孤児に送ろうと決めました。決めた途端、まるで全てが準備されていたかのように協力者が現れ、とんとんと話が進みました。アメリカは中国とのしがらみが日本より少ないので、支援をしやすい環境でもありますね。
―理麻さんの知るダライ・ラマ法王を教えてください。
藤田理麻:猊下の並大抵でない洞察力にはいつも驚かされます。あるイベントで、100人近い参加者がいる中で、裏方の仕事で人知れず苦労していた私の友人に目を留めて、すっと歩み寄って「ごくろうさま」と言った話は私が最も好きな猊下のエピソード。あと、相手が有名でも、市井の人でも、誰に対してもまったく同じ態度を取られるのもすごいと思います。言葉と行動が完全に一致している方ですね。
―今後の展望は?
藤田理麻:チベット支援は、ライフワークとして死ぬまで関わっていきたいです。今は絵本を作ってっていますが、そのうちeブックになるかもしれませんね。時代と共に変えていくこと必要はあると思っています。私にとって絵は道具ですから、その道具を使って役に立てられることがある限り、やり続けるつもりです。
※このページは「2017年7月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。