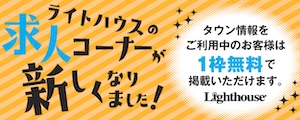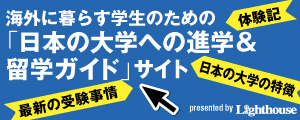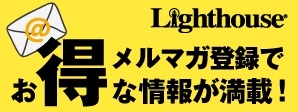(2025年2月号掲載)
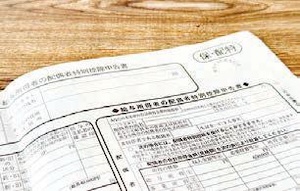
年収103万円の壁の見直しは2025年分所得(2025年の年末調整)から始まる予定。
|
103万円の壁は、
何が問題だったのか
前回の総選挙の際に、自民党は大敗して現在の石破内閣は「少数与党」となっている。一方で勢力を伸ばした国民民主党は「手取りを増やす」政策が有権者から支持された。具体的には「103万円の壁」を引き上げるとして、この公約を実現すべく延々と論争が続いている。この「103万円の壁」とは、パートやアルバイトで働く人が扶養控除を受けられる境界となる金額のことだ。配偶者や扶養する子がこの壁を超えると、納税者本人が税金を払うだけでなく、彼らが扶養家族から外れ、一家の所得税にも影響する。つまり、パートやアルバイトなどで、この「壁」を超えてしまうと世帯全体の「手取り」は減ってしまう。
そんな中で、この「壁」というのは、大きな政治課題になってきている。103万円以上働くと世帯として「かえって損をする」とか「働き控え」が発生するというのは、やはり理不尽だからだ。そこで国民民主党は、この「壁」を178万円まで引き上げるべきだという要求をしている。けれども、財務省や財務省に近い自民党議員などは「『壁』の引き上げは明らかな減税なのだから財源がなければできない」と拒否している。現時点では123万円まで「壁」を引き上げるというラインで予算案が組まれつつある。
最終的にどうなるかは予算審議の成り行き次第だが、このように財務省ができるだけ国の借金を減らそうと動くと、最近は「ザイム真理教」などと世論から批判を浴びる傾向がある。また税制調査会などで「壁の引き上げ」に反対した議員には、次の選挙へ向けて厳しい目が向けられようとしている。確かに、経済が低迷し国民の所得が伸び悩む中で、この種の減税への希望が拡大するのは理解できる。
だが、海外から見ていると議論はそう簡単ではない。まず、アメリカの税制と比較すると、日本も共働きが主流の社会になったのだから、配偶者控除など止めて夫婦合算課税にした方が、それこそお互いに「壁」など意識しないで働けるだろう。子どもも18歳で税制上の扶養から外す代わりに大学の学費負担を特別控除で救うほうが理にかなっているように思われる。
103万円の壁崩壊後、
何が起こるか
それよりも深刻なのは財源の論議だ。日本の野党や世論の大勢は、国の借金というものを軽く考え過ぎている。確かに国債による借金は大きいが、日本には個人金融資産があるので相殺されているから大丈夫という議論がある。間違いではないが、この状況がいつまでも続くと思ったら甘い。やがて海外に国債を売る時が来るし、その場合はドル建てにしないと調達は難しくなるかもしれない。そうなれば、日本の財政事情はさらに悪化する。
何よりも金利政策が問題だ。今は日米の金利差が縮まらないので円安が進んでいるということになっている。しかし、仮に日本が金利を上げると、国債の金利も上がってしまう。日本の国債の残高(借金の総額)は約1100兆円ある。仮に国債の金利を1%上げると、毎年11兆円のカネが必要になる。日本の毎年の国家予算は約110兆円なので、国債の利払いにその10%が上乗せされる。その一方で、今回の「壁」を仮に野党案の178万円まで引き上げるには、財源として8兆円程度が必要とされている。仮の話だが、金利アップと「壁」の引き上げを同時に行えば、1年で約19兆円が吹っ飛ぶ。
既にGDPに対する借金総額では、日本は先進国では最悪となっている。その日本でここまで財政を緩めてしまっては、最悪の場合に円は投機の売りを浴びせられて1ドル200円などという水準まで下がる危険もある。もちろん、日本経済は今でもGDP世界4位の規模を維持しており、アルゼンチンやギリシャのようにはならない。けれども、ウォール街の現場には「日本の繁栄を知らない世代」が増えているのは事実で、彼らの日本への見方には厳しい視線がある。日本の財政論議は直接的には為替レートにも影響を与えるわけで、在外邦人にも他人事ではない。
|