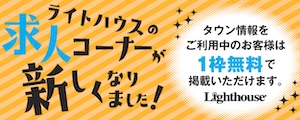新しい時代劇か? 昭和風情の勧善懲悪ドラマ

東京中央銀行本店こと三井本館は重要文化財。番組では、この建物の上にCGでビルを加えている。
|
日本では、TVドラマ『半沢直樹』が大ブームである。各回の視聴率は20%を大きく超えており、本編の制作が間に合わず急遽放送された「出演者による座談会の生放送」も22%以上の視聴率を稼いだという。7年前の第1シーズンも大きな反響があったが、今回のシーズンはそれを上回る勢いだ。
内容についてはテレビジャパンでも放映されているので、ご覧になった方も多いと思うが、半沢直樹という銀行員が行内の派閥抗争や、内外の不正行為などに巻き込まれながら正義を貫いてゆく話だ。悪はあくまで悪どく、主人公はギリギリまで追い詰められるが、自身の機転と粘り、そして友人など周囲の助けもあって、最後には悪人を土下座に追い込む。ドラマとしては、メリハリが効いていてスピード感もあるし、各回1時間の中にもサプライズが仕掛けられていて作りは丁寧だ。
だが、それだけでは、ここまでの人気の理由は説明できない。一体何がこのドラマを大ヒットへと押し上げているのだろうか。
1つの理由は、題材は現代であるものの、ドラマとしての本質は時代劇と変わりないということだ。権力は悪で庶民は善という前提で、勧善懲悪劇で権力を罰するドラマはフラストレーションの解消になる。そんな構造が江戸時代から綿々と続いた日本の伝統だとすれば、この『半沢直樹』は正にそのフォーマットに忠実に従っていると言える。今回のシーズン2は、花形級を含めた歌舞伎役者が4名参加しており、大見得を切るかのような「顔芸」や、歌舞伎の伝統である掛け合いのリズム感などを取り入れていることが余計に「時代劇」の風情を伝えている。「倍返しだ」などの決め台詞や、悪人への証拠の突き付け方は、『水戸黄門』や『遠山の金さん』『大岡越前』など江戸を舞台とした時代劇そのものだ。
2つ目の理由は、そこに昭和の価値観が重ねられているということだ。銀行員はあくまで背広とネクタイ、大きなカバンを下げて汗を流しながら外回り、悪事の証拠は印鑑を押した書類のコピー、会議となれば関係者一同が集合してダラダラということで、あらゆるところに前時代感が漂う。極め付けは主人公の妻が専業主婦という設定であり、現代との隔絶感は否めない。第2シーズンになって、テック関連企業が出てきたり、システムのセキュリティー問題が出てきたりしたが、依然として、パスワードをLINEで送るなどといった現代ではあり得ないシーンもあり、少なくとも令和の時代を感じさせるものはない。
ノスタルジーだけではないこのドラマの魅力
3つ目としては、妙に豪華な点がバブル時代への懐しさを感じさせるという点だ。銀行の会議室や頭取室は非現実的なぐらいに豪華であり、本店の中央階段に至っては国立博物館を借りてロケをしているだけあって、信じられないスケールである。行内の密談に際しては、役員クラスになると高級料亭が使われるし、中間管理職クラスでもかなり高級な料理屋が登場する。実際の日本のメガバンクは、現在はフィンテック(金融の電子化)改革の激動の中にあり、実店舗の大規模な閉鎖、人員の急速な整理、通帳有料化によるペーパーの追放など厳しい過渡期にあるのだが、そんな気配はまったくない。
では、多くの視聴者は過去のノスタルジーに浸るだけのために、熱心にこのドラマを見ているのかというと、そうでもないようだ。管理能力のない上司、無理難題を吹っかける発注元、消費者による執拗なクレームなど、現代日本のビジネスの現場には、ストレスが溢れている。合理性や正論が通らず、非効率が放置される状況も相変わらずだ。そんな中で、最後には正義が逆転勝利を収める勧善懲悪劇は、万人受けする普遍性を持っているのだろう。異なった社会にいる我々には、その全体構造を改めることが大切と伝える役目があると思うが、日本で苦労している個々人のストレスには理解と共感を寄せるようにしたい。そんな観点からも、このドラマは十分に楽しめる。
|
(2020年10月1日号掲載)
※このページは「ライトハウス・ロサンゼルス版 2020年10月1日」号掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。