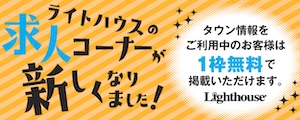(2022年4月1日号掲載)
水際対策、国内からの支持、海外からの目

成田空港国際線の旅客者数は19年度から20年度にかけて96%減だった。再び賑わうのはいつか?
|
日本という国は世界の中でも「国境の壁」が低い国として評価が高かった。外国人への入国審査は甘くはないが、理由なく入国が拒否されることはなかったし、2019年まで毎年4000万人近い訪日観光客を受け入れていた中で、入国審査が大きな問題になったことはない。一方で、日本のパスポートがあれば、世界のほとんどの国で特に問題なく入国ができることから「滑りがいい」と言われていた。
だが、新型コロナウィルスの感染拡大により現状は激変した。最初にお断りしておきたいのだが、今回のオミクロン株流行に伴う水際対策について、初期の対応については否定するつもりはない。12月初旬の時点では、感染力が強く強毒性の変異株という最悪の事態が否定できなかったからだ。また、ワクチン接種の加速や医療体制の確保のために時間稼ぎをする必要があった。
その後、オミクロン株には著しい強毒性は認められないことが判明し、日本国内でも市中感染が拡大する中で、「鎖国」をする意味はなくなった。にもかかわらず、以降も厳しい水際対策は継続された。日本国籍者でもアメリカから入国する場合は3〜6日の強制隔離を含む10〜14日の待機期間が課せられた。また外国籍の場合は原則入国禁止が続き、重要な商談のための出張者も、入試に合格して日本の大学生の身分を得ている若者も入国拒否が続いた。特に留学生に関しては最大で15万人が国外待機となっていた。
理由は、世論が圧倒的に支持をしたからだ。21年夏に感染拡大の中で夏季五輪を開催したことへの反発は、大会後も続いた。一部の野党が「完全鎖国でゼロコロナ」というスローガンを掲げていたのもこの時期だ。岸田内閣はこうした声を意識したのであろうが、結果的に水際対策は好評となり支持率が60%を超えた。客観的な意味がなくなった以降も、なかなか停止ができなかったのはこのためだ。
この間、世論には「島国である日本の特質を生かした水際対策」は強力に実施すべきだという声が多く見られた。だが、国外から見れば、これは裏返しとなる。「島国である日本は、緊急時には国境を閉ざして鎖国する可能性が高い」という見方をされても仕方がない。例えばアメリカの大学の中には、日本を交換留学の対象から外す動きも出ていた。
民の受け入れも世論が足かせに
さらに2月末にはウクライナ侵攻が勃発した。岸田内閣は、国際社会と協調してウクライナへの支持と支援を表明した。だが、戦争難民の受け入れは当初8名からのスタートとなった。日本国内に身元引受人がいることが条件とされたからだ。そんな中、世間には「偽装難民が紛れ込む危険がある」などという声もあった。また、ロシアやウクライナから緊急避難する日本人の避難者については「水際対策の上限入国者数の別枠」になるという。当然だが、根回しのように事前に発表するのは違和感を覚える。
日本は元々、そこまで「国境の壁」の高い国ではなかった。例えば1910年代にロシア革命が起きると、避難民約8000人を移民、つまり白系ロシア人として受け入れた。また第二次世界大戦中は、外交官の杉原千畝がポーランドなどから避難するユダヤ人に日本の通過ビザを発給して少なくとも4000人の避難を助けた。彼らの多くは敦賀や下関で日本に上陸し、その後、当面の目的地である米国や上海に向かった。また、ベトナム戦争終結後には約1万1000人のインドシナ難民を定住難民として受け入れている。
こうした歴史を考えると、現在の対応は異例だ。このままでは、日本は国際社会から敬遠されるし、日本のパスポートの滑りの良さが守れるかも不透明だ。コロナ禍への不安が、強度の内向き志向に転じているのは分かる。しかし、それはどこまでいっても感情論であり、与野党問わず、政治はこれを利用すべきではない。反対に日本の国益を考えた判断を国民に対して説明するのが政治の責任ではないだろうか。
|