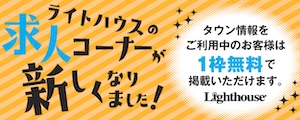(2025年1月号掲載)

『SHOGUN』のロケ地は、バンクーバー島の太平洋側。温帯雨林の森が広がり、冬は雨が激しい。
|
忠実に日本文化を再現
経済効果も期待できるか?
真田広之氏が制作し、主演も務めたTVシリーズ『SHOGUN』は、世界で配信されたドラマシリーズとしては歴代1位の再生回数を誇るなど大成功で続編の企画も決まっている。エミー賞では、作品賞、主演男優賞(真田広之)、主演女優賞(澤井杏奈)など18冠を獲得、さらにゴールデングローブ賞でも有力と言われている。
このドラマは1980年に制作された同名作品のリメイクであるが、演出の方針は全く異なっている。真田氏は、徹底してホンモノにこだわり、日本人の役は全て日本語のセリフとして吹き替えをせず、英語圏への配信には字幕で対応した。また、衣装、小道具、所に至るまで日本文化の忠実な再現を心がけたという。
実際の作品では、関ヶ原の戦い前後の日本の政治情勢と同時に、まるでシェイクスピア悲劇のように人物の苦悩や葛藤が描かれている。アメリカでは『Game of Thrones』を超える緊迫感のある心理劇という評価もある。
一番評価したいのは、前回の1980年の際には武士の時代の日本人の描き方が、アメリカ視点からの「エキゾチック(異国趣味)な世界」と言われても仕方がなかったのが、今回は400年前の日本人を等身大の人間として描き尽くしたということだ。併せて、徳川政権が成立した背景には、カトリックとプロテスタントの闘いがあり、家康(劇中では虎永)は、その両者の争いを見抜いて日本の独立を守ったという歴史観を採用していることだ。これは、最新の歴史研究の成果を取り入れたものと言えるし、アメリカ人にも当時の日本の歴史に親しみを持たせることに成功している。この『SHOGUN』の成功は、城址めぐりなど改めて日本観光のニーズを掘り起こすであろう。
日本の時代劇とは
一線を画す映像と演技
良いことばかりが目立つこの『SHOGUN』だが、気になる点もある。それは、本作が日本の時代劇のスタイルを変えてしまったということだ。具体的には、映像と演技の二つの面においてである。まず、映像だがカナダのバンクーバーに大きなセットを組んだだけでなく、最新の高感度カメラを使用して光と闇の映像美を実現している。さらに、甲冑にしても衣装にしても新品ではなく「使い込んだ」状態を作って極めてリアルな表現をしている。これは日本の映画にしても、大河ドラマや捕物帳などのTVドラマにしても、全くなかった種類の映像表現だ。特に、ろうそくの光だけを使って緊迫した心理戦を描くシーンなどは、まるで17世紀の世界が現代に蘇ったようなリアルな迫力がある。
一方で演技に関しては、脚本は日本の時代劇の書き方と変わらないものの、発音やアクセントは完全に現代日本語にしている。これも日本の時代劇の伝統とは異なる。テレビにしても映画にしても、日本の時代劇というのは、歌舞伎などの舞台芸術の伝統の延長に作られている。だから、衣装はあくまで舞台衣装であり、16世紀や17世紀の世界を再現するような「着古し感」などはつけない。原色のまま、衣装倉庫から取り出したままのフィクションの世界である。セリフも、どこか歌舞伎の言い回しのようなリズムやドラマ性を与えてある。
どうして、時代劇の映像作品が舞台芸術のようなフィクションの空間で作られているのかというと、伝統文化の尊重という意味もあるが、まず、視聴者にそのような期待がある。また、合戦や切腹といった血なまぐさいドラマを、フィクション化することでマイルドにするという意味合いがあるからだ。
一方で今回の『SHOGUN』は、スーパーリアリズムの映像美と、徹底して現代の口語日本語アクセントで通すことで、当時の人物の心理を、現代人に直接に訴えかけるようにしている。実はそんな伝統は日本のエンタメ界にはなく、これはこの作品の独創である。結果としては見事な説得力を獲得しているが、この点に関しては、賛否両論があってもおかしくないであろう。
|