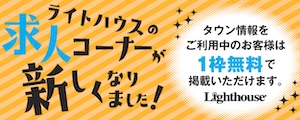(2024年7月号掲載)

日本の学生の就活の早期化が問題となり、2021年以降は政府が就活日程の指針を出している。
|
昭和から令和へ
変わりつつある労働環境
安倍政権時代に始まった日本の「働き方改革」では、まず長時間労働の根絶が進んだ。現在では時間外勤務への厳しい規制は運輸業界にも及んでおり、サービスを落としても労働者を守るという方針で改革が進んでいる。その一方で、事務部門では時短だけでなく、さまざまな改革が進んでいる。
まず、パワハラ、つまりパワーハラスメントについては、禁止法もできて一気に意識改革が進んだ。昭和から平成前半までは当たり前とされた、新入社員などに威圧的な指導を行う上司などは、急速に姿を消しつつある。セクハラももちろん同じように追放されつつある。嫌がる若手を宴会に誘うのはご法度という企業も出てきた。
さらに、少子化が進む中で日本は人手不足が慢性化している。そんな中で、就活の状況は圧倒的に「売り手市場」つまり企業よりも就活生が有利な状況となった。これを受けて、1990年頃から30年間ずっと22万円前後で据え置かれていた大卒の初任給が上昇している。20万円台の後半という企業も多くなり、金融やコンサルの関連では初任給が年俸で400万円以上という企業も登場している。
新入社員に対して、配属先を確約するケースも出てきた。新卒一括採用で数十人とか数百人を採用する企業では、多くの職種に新入社員を配属して、その後、営業とか、開発、総務などさまざまな職種を経験させて、何でもできる「ゼネラリスト」に育てるというのが日本流だった。だが、意に沿わない職種に配属すると、連休明けに辞めてしまう新人が続出する。そこで、希望職種への配属を売り物にして採用をする企業が出てきたというわけだ。
さらに、現在の日本はほぼ完全な共稼ぎ社会となり、転勤を嫌う人も増えてきた。従って、職種だけでなく勤務地も確約して、例えば東京で採用したら以降は転勤はさせないといった条件を提示する場合もあるという。辞令一枚で転勤を命じられたり、技術職を期待して入社したのに最初は営業から「叩き上げる」などと言われた時代とは様子がかなり変わってきた。
アメリカ流の働き方は
日本で定着するか
では、日本企業の「働き方」は良い方向に向かっているのかというと、これはその通りだと思う。だが、心配な点も多い。一つ目は、集団主義をどう変えるのかという問題だ。宴会参加の強制を止めたり、新人といえども個人の人格を尊重するというのは無条件に正しいと思う。だが、そのような個人主義が機能するには、アメリカのような厳格な契約概念と、本当の意味でお互いに人格を認め合う文化が必要だ。
年齢や社歴での上下関係を残しながら、ハラスメントには気を遣い、そのくせお互いの職務範囲は重なり合って相互に助け合うというのは、正確に言えば筋が通らない。人間関係は濃密で、仕事は相互依存があり、そのくせ気を遣うというのでは、息が詰まりそうだ。ここはやはり、職務範囲を個人に割り当てて、お互いの仕事には手出しをしないアメリカ流の方が合理的だろう。
日本の場合、希望の職種に配属するにしても、医学部や教職課程、理系の研究職を除くと大学の教育がそのまま企業で生かされることは少ない。そうなると、希望の職種に就けるといっても、本人には知識やスキルは身に付いていないわけで、実際の教育は企業に入ってからだし、内容も企業ごとの自己流が主になる。これでは優秀な専門職による「ジョブ型雇用」の社会にはなかなか届きそうもない。
初任給アップにも裏があり、月給30万円とか年俸500万という場合には、その後の昇給はごく僅かだったり、職種を変わると減俸するという企業もあるようだ。これもスキルのある専門職ごとに「労働市場」が形成されていないからだろう。いずれにしても、日本の「働き方」は変化の季節を迎えている。この際、日本式にこだわらずに、スキルを評価し、個人に仕事を割り当てる世界標準の「ジョブ型雇用」を一気に導入するのが一番混乱が少ないと思うのだが、そう簡単ではないようだ。
|