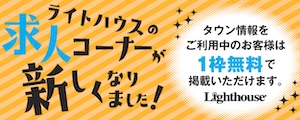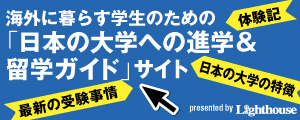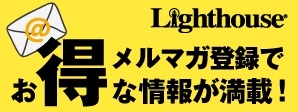「プロダクトに対して純粋」であるべき。
デザイナーのエゴは、現場に伝わります。
日本で大手ジーンズメーカーに勤務し、ジーンズ制作のいろはを学んだデザイナーの松原正明さん。デニムジーンズの本場でデザインをしてみたいと渡米し、プレミアムジーンズを製造するAG Adriano Goldschmied, Inc.社に入社。「エゴを出さないのが僕のスタイル」と謙虚に語る松原さんに話を聞いた。
|
【プロフィール】まつばらまさあき◉東京都出身。日本の大学で経済学を専攻した後、大手ジーンズメーカーに入社。企画生産部に配属される。2007年にプレミアムジーンズ「AGジーンズ」を製造/販売するAG Adriano Goldschmied, Inc.転職のため渡米。以来ヘッドデザイナーとして、同社で活躍中 |
ジーンズ発祥の地で一度は働いてみたい
大学は経済学部を出ていて、卒業後は大手ジーンズメーカーに入社しました。ですから、ジーンズに関するノウハウは、すべて社会人になってから覚えたんです。元々洋服が好きで、特にジーンズが好きだったのが、入社のきっかけでした。企画生産という部署に配属され、デザインだけでなく、初めは生産やアシスタントなど、色んなことを経験しました。
デニムジーンズ発祥の地である西海岸には、出張や個人的趣味もあって何度も来ていました。それで業界の色々な方たちとお話しする機会にも恵まれて、ひょんなことから今の会社(AGAdriano Goldschmied, Inc.)で働くことになりました。
AG Jeansは、ロサンゼルス初のプレミアムジーンズ・ブランドで、社名になっている有名なデニムデザイナー、アドリアーノ・ゴールドシュミットと、アメリカ有数のデニム工場、Koos Manufacturing Inc.が合併して誕生しました。そういう経緯で生まれたブランドですから、縫製、ウォッシュ加工の工場が、デザインオフィスと一緒になっているという、稀で、恵まれた環境にあるんです。「ここなら思いっ切り、力を発揮できるかも」という感覚になりましたね。
西海岸はジーンズ発祥の地で、歴史もあります。ジーンズに関わっている者なら、誰もが一度は働いてみたいと思いますよね。それまで日本のブランド一筋で11年間ずっとやってきましたから、今度は異なるグラウンドで、チャレンジしてみたいと思い、渡米を決意しました。2007年のことです。
ファーストサンプルでも 即商品化される

松原さんデザインの今年のコレクション
|
こちらで働き始めたら、渡米前とはずいぶんイメージが変わりましたね。もちろんアメリカはやっぱりスゴイのですが、本場に来て初めて、日本のジーンズの水準の高さに驚きました(苦笑)。どちらが良い、悪いということではなく、「違い」はやっぱりあります。例えば、アメリカは決定から商品化のスピードがとても速い。日本では散々考え抜いて決定を下すわけですが、ここでは「イイと感じたら、考え抜く前にやってみよう」っていう感じで、決定が単純明快です。
僕がサンプルを作って、「こういうデザインでやりたい」と言った時に、日本だったら「こんな物もある」「こういうサンプルの作り方がある」とか色々意見が出てくるんですね。でも、ここでは、「作ったんだから、さあ売りましょう」と、ドンドン先のステップに進んでいきます。うちの会社は、工場とオフィスが一緒になっている環境が恵まれていると言いましたが、デザインしたサンプルは、急げば2日以内に上がってきます。通常は外部の工場に送って、最速でも1週間はかかります。ただし、その分、すぐに決めていかなくちゃいけないのですが…。
また、日本で働いていた時は、自分がファーストサンプルを作っても、それがすぐに商品化されることはなかったです。最初のサンプルからもっと練り直して、またサンプルを作って、やっと皆にプレゼンして、そこで会議にかかって、ようやく商品化でした。今は、最初のサンプルの出来が良ければ、いきなりマーケットに出されることもあります。だから、ファーストサンプルを作る時に、時間がない中で、自分の持てる物を全部注ぎ込まないといけない。のんびり考えている暇がないほどスピードが速いです。「もっとじっくり作り込ませてほしい」と思ったこともありましたが、このペースで全体が動いていますから、僕だけが時間をかけて、歩調を乱すわけにはいきません。
嗜好の部分での違いもありました。日本で人気のあるフィットや素材と、アメリカで人気のあるものは全然違いました。日本と同じようにいけるだろうと思って来ましたから、戸惑いましたね。感覚の違いでしょうか、売れる物がやはり違うんですね。日本で、「これなら絶対売れる」という鉄板的なアイデアがあっても、アメリカでは全然売れないこともありました。そういう違いを理解するのに苦労しました。
最初の1年くらいは、それでミスをしました。知識があってもミスしちゃうんで、悩みましたね。ですが、大きなミスにならずに済みましたし、今もそうですけど、当時から会社の売上が伸びていて、前向きな失敗はある程度許容する流れにあったのは幸いでした。
現在、ヘッドデザイナーとして、デニムに関することは、全部僕が最終決定をしています。アシスタントデザイナーが数人いますので、彼女たちと一緒に生地を選んで、デザインを起こして、パタンナーと打ち合わせして、フィッティングして…。その生地が上がったら、ウォッシュの開発をします。そうして季節ごとに年4回のコレクションを作り上げるのが大きな仕事です。リサーチやコレクションを出品している展示会に出るために、ヨーロッパやニューヨーク、日本にも出張します。
ムダを省くのが僕のスタイル
ジーンズのデザインは、基本的にLevi’sの5ポケットがベースとして存在します。素材にしてもデニムに決まっていますから、その中でどうするかです。あとはウォッシュという色の洗い落としで差別化を図るしかありません。素材のデニムを擦ったり、石と一緒に洗ったり、ブリーチをかけたりして色を落とすという作業をどういう風にするか、そこに個性が出ます。染め方によって落とし方も違いますし、糸の作り方によって擦り方が違ってきたり。他の洋服のデザインとは、かなり異質なものですね。
基本的に僕は、デザインに我を出さないようにしています。デザインに我を出すと、それは値段に跳ね返ってきます。なぜなら我を出すということは、何かを付け加えることになり、それはコスト増を意味します。できる限りムダを省くというのが、僕のスタイルです。それが個性と言ったら個性かもしれないですね。プレミアムマーケットでは、珍しいデザイナーなのかもしれません。
例えば個性を出したいのであれば、クオリティーの高いボタンを使うとか、良い素材を使ったり、そういうところでプレミアム感、圧倒的な違いを出したいと、僕は思います。うちのジーンズは1本200ドル以上、300ドル台の商品が多いですが、実際使っているボタンはイタリア製、素材も7~8割は日本の物を使って品質にこだわっています。
この仕事をしていてやりがいを感じることは、日本で初めてデニムを自分で企画して作った時から変わらないです。それが売れて、誰かに履いていただけることです。今は、それに加えてAGジーンズというブランドがうまくいくことが、うれしいですね。
経験を積むエゴを出さない
デザイナー志望の人にアドバイスですか?僕が言うのもなんですけど、「経験を積む」ことが大切かもしれません。うちのインターンの子たちを見ていても、経験を積んでのし上がってやるという強い想いをすごく感じますね。チャンスはいっぱいあると思いますよ。特に日本人でしたら、それくらいの積極性がないと、ただでさえ言葉や文化でハンデがあるわけですから。遠慮していては、やっていけないでしょうね。
あとは、先にも言いましたが、デザインで「エゴを出さないこと」でしょうか。「ここをこうすれば、自分をアピールができるんじゃないか」。そういうものは、実は余計であることが多い。デザイナーのエゴが入ると、製造現場の人たちって気付くんです。そうすると、現場から信用されなくなります。だから、「プロダクトに対して純粋」であるべきなんです。現場から信頼されれば、必ず良い物が上がってきます。難しいことかもしれませんけど、そういう純粋さが大切です。
(2012年7月1日号掲載)