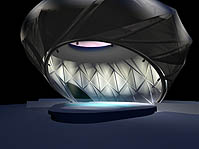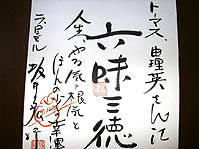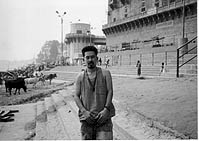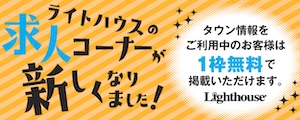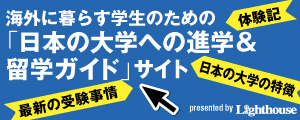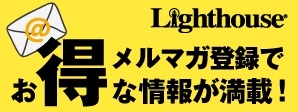|
今回は、ローンオフィサーの横山貴恵さんを紹介。日本での事務職に満足できず、野心を抱いてアメリカに留学。JPモルガン・チェース銀行の中で、日本文化を理解するローンオフィサーとしての活躍について聞いた。
|
【プロフィール】よこやま・たかえ■京都府出身。京都女子大学を卒業後、大手製薬会社に就職。退職後、米系半導体・精密機器の商社に勤務する。1998年、留学のため渡米。サンタモニカ・カレッジを経て、UCLAで社会学の学士号を取得。2003年に卒業後、JPモルガン・チェース銀行にローンオフィサーとして就職、現在に至る |
そもそもアメリカで働くには?
- アメリカで働くためには、原則として合法的に就労可能な「ビザ」が必要になります。
アメリカ・ビザの種類と基礎知識 - 日本から渡米してアメリカで働く方法として、18ヶ月の長期インターンシップも選択肢の1つ。
アメリカでワーキングホリデーのように働く!「J-1ビザインターンシップ」徹底解説
キャリアを磨くため
日本を脱出、留学

社会学のバックグラウンドも
キャリアに役立っている (UCLAでの卒業式にて) |
日本の大学を卒業後、学校の紹介で製薬会社に就職しました。アメリカの医薬品を日本で販売する大手企業でしたが、女性はあくまでもアシスタント的な役割。当時は、どんなに優秀な女性も昇進の難しい時代で、やる気のある女性は皆同じような悩みを抱えていました。私も、この先、何年働いても同じだろうと見切りをつけ、3年半で退社しました。
その後、米系の半導体を扱う商社に入り、カスタマーサービスの仕事をしました。社内には帰国子女も多く、雰囲気は前の会社より良かったのですが、やはり日本的な社風は変わらず、「日本を出よう」と決意しました。
そして、1998年に渡米。UCLAでソーシャルワーカーになるべく、社会福祉の勉強をしました。ところが卒業した頃は、社会福祉に対する国の予算が非常に少なく、新規職員の採用が凍結されていたこともあり、その分野での就職も難しくなっていました。迷っている時に、義理の姉の紹介で、チェースのマネージャーからローンオフィサーの就職口をいただいたんです。
求人の応募要項には、ファイナンスのキャリアが3年以上、英語力もかなり要求されるとありました。「私は要求される条件に見合わないと思う」と伝えたのですが、「とりあえず、おしゃべりしに来てください」と言われて出向くことに。そして、面接の1時間のうちに気持ちがすっかり変わったんです。
マネージャーによると、ローンオフィサーの仕事は借り入れの相談から契約、返済の相談といった一連の流れに携わるのですが、そのなかでも、カスタマーサービスが非常に大切であり、今、社として日本人を始めとする顧客の言葉や文化が理解できる人を必要としているとのことでした。実際、社内には財務や経済のみならず、社会学や心理学を学んできた人も多いんです。顧客と密着して働く仕事なので、金融の知識があるだけでなく、信頼関係を結べないといけない、社会学のバックグラウンドも十分に役に立つと言われました。また、金融関係のシステムについては、トレーニングするので心配はいらないとのこと。お客様の手助けができるのなら、と入社を決めました。
大切なのは顧客やチームとの
緊密なコミュニケーション
入社後はまず、ローンの申請書類を処理するプロセッサーのアシスタントから始まりました。分厚い申請書類や契約書をコピーしながら、書類の内容や実務、具体的な銀行手続き、その中身について学びました。同時に会社のトレーニングプログラムを受け、ひたすら勉強しました。
ローンオフィサーは、ローンを必要とする顧客を開拓しなければなりません。また、お客様がいたとしても、実際にローンが下りなければ、お役に立ったことにはなりません。お客様のコンサルテーションが始まったら、住宅購入期間のおよそ30日間、ローン承認までお世話することになります。顧客開発に営業やマーケティングは大切ですが、おかげさまで、これまでのお客様からの紹介や、信頼関係のある不動産エージェントの方などから紹介を受けることが多いですね。
私の日課はまず、朝1番にEメールをチェックし、問い合わせのあったお客様の所に出向きます。そしてオフィスに戻って、進行しているローン申請の進捗を確認します。一旦お客様がローン申請を始めたら、私の下でさまざまな専門分野をカバーする担当者たちが動き出しますし、社外でも不動産会社やエスクロー会社、タイトル会社など、多くの人が関わってきます。私はその一部なので、ローンの進行を確認するのは肝心なこと。1日でも遅れると、信頼関係が損なわれてしまいます。
複雑な仕事ですし、自分でコントロールできない部分も多いので、ストレスも重なります。社内では調和を保ちつつプロセスを進め、お客様には安心してもらえるように対応していかなければなりません。お客様のことを考えると、眠れない時もあります。気が付くと、朝から晩まで、土日も仕事しています。
とはいえ、自分の裁量で勤務時間を決められるという利点はあります。また、やったらやっただけの報酬がいただけるので、やりがいもあります。ノルマもありますので、今のような時期は特に厳しいですが。男女の差がないところもいいですね。勉強するのも、昇給するのも自分次第。それに合わせて、会社がトレーニングを提供してくれるところも恵まれています。
ですが、競争相手も多いので、どこか違ったサービスを提供していかなければなりません。私は常に丁寧に、気持ちを込めたサービスを心がけています。お客様と出会えたご縁を大切にしています。やはり家の購入は人生においてそう何度とない大切な買い物です。お客様が心理的に不安定になったり、心配されたりすることが多いのですが、緊密にコミュニケーションを取って、不安要素を解消できるよう努力しています。
アメリカンドリームを
実現させる手助けに
家を買うというのは、誰にとってもアメリカンドリームです。その第一歩が資金計画。住宅ローンの仕組みを知って、無理のないプランを立てるのがとても大切です。そのお手伝いができるというのは本当に光栄なことです。皆さんが夢に向かって頑張っておられる姿に、こちらもいいエネルギーをいただいています。
これからも精神的・経済的に自立した女性でありたいと思っていますし、家庭も大切にしたいですね。また、仕事の面でも、お客様にもっと信頼してもらえるよう、自分なりに努力を重ねていきたいと思っています。この仕事は人に会うのが好きな人、接客が好きな人に、とても適しています。数字は毎日見るわけですから、すぐに強くなれます。逆にあまり数字に気持ちが向いていると、良いカスタマーサービスができないと思うんです。それよりも、お客様と色々な話をして、相手の立場になって考え、提案できることが大切だと思います。
(2009年3月1日号掲載)