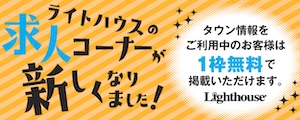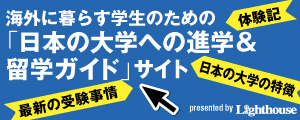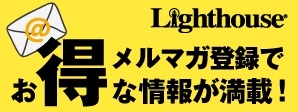アメリカの学校に子どもが通い始めた時に戸惑うのが授業スタイルの違いです。日本の講義型の授業とは異なり、アメリカは参加型(アクティブラーニング)が一般的です。生徒には、議論に参加すること、意見を発言することが要求されます。黙っていると「理解していない」「考える気がない」「参加する気がない」とマイナスの評価をされてしまいます。
先生は、「本当に正しいのか」「他に考えはないのか」「他の見方はないのか」と繰り返し生徒に問います。情報を鵜呑みにしていないか、他人の意見に流されていないか、判断に偏りがないか、生徒に「問い」を重ねることで、思考を再評価する習慣を身に付けさせようとしています。
日本人の子どもの多くは、英語力に問題がなくても、あまり議論に参加しようとしません。日本人は集団の和を重視しますから、意見を戦わせることが苦手なのです。和の精神は素晴らしいのですが、議論に参加しないと「やる気がない人」というレッテルを貼られてしまいます。子どもがアメリカの学校教育を受けるのであれば、家庭で「自己表現力」を育てておくことが大切です。
子どもに話をさせる
表現する力を育てる最初のステップは「たくさん話をさせること」です。まず親が聞き上手になりましょう。子どもが話をしたがっている時に「忙しいから後にして」なんて言わないでください。子どもの目を見て真剣に話を聞いてあげましょう。
幼い子どもは支離滅裂な話をしたり、話があちこちに飛ぶことがありますが、急かしたり、批判したり、訂正したりせず、十分に話す時間を与えてください。また、うなずいたり、共感したり、感嘆したり、相づちを打ったりしながら聞くと、子どもはどんどん自分から話を広げてくれるようになります。
子どもは自分の考えを親と共有することを心から望んでいます。親子の日常的な会話、子どもの気持ちや意見を大切にすることで、子どもが生来持っている「自己表現したい気持ち」を引き出し、伸ばしていくことができます。
親が上手に質問する
また、親子の会話の中に「問い」を増やすことを心がけてください。例えば絵本を読みながら「ママはこの絵が好きだけど、◯◯ちゃんはどれが好き?」と質問します。子どもは「ボクはこの絵が好き!」と答えます。すかさず「◯◯ちゃんはどうしてこの絵が好きなの?」と質問を重ねます。
「問い」を繰り返すことによって、子どもは深く考える習慣を身に付けることができます。「ママはリンゴが好きだけど、◯◯ちゃんは何が好き?」と聞けば「バナナが好き!」と答えます。すかさず「どうしてバナナが好きなの?」と聞きます。すると「甘いから」「黄色が好きだから」と理由を考えてくれます。
質問のポイントは尋問しないこと。「今日学校で何をした?」「誰と遊んだ?」「何を食べた?」と一方的に聞かれると子どもは答える気を失います。「ママは今日お買い物したけど、◯◯ちゃんは何をした?」「ママはお昼にトーストを食べたけど、◯◯ちゃんは何を食べた?」というように「ママはこうだけど」と言ってから、質問してください。
考える力は自分らしく生きる力
自分で考える力を伸ばすことは、子どもが自分らしい人生を生きることにつながります。自分は何が好きなのか、自分は何を信じるのか、自分は何をしたいのか、どんな人生を歩みたいのか、自分自身をより深く理解できるようになります。
周囲の意見や社会通念に流されることなく、自分で考え、自分を信じて行動する習慣を持つことは、自らの意思で進路を選択していくことにつながります。その結果、自分の生き方を見つめながら目標に向かって真っすぐに進むことができる、自分らしい人生が実現できるのです。
(2016年10月1日号掲載)