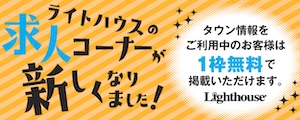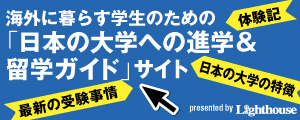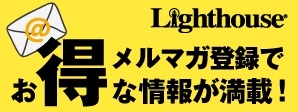フジコ・ヘミング◎コンサート直前インタビュー
演奏の中に詩や語りが入ったり色彩を表現しています
日本人ピアニストの母とスウェーデン人の父との間に生まれたフジコ・ヘミングさん。幼少の頃からピアニストとしての才能を発揮し、天才と賞賛される。耳が聴こえなくなるなど困難に見舞われたが、ピアニストになる夢は諦めず、プロデビュー。情感あふれる独特な演奏スタイルから「魂のピアニスト」と呼ばれ、絶大な人気を誇る。3年ぶりのアメリカツアーでロサンゼルスを訪れるフジコさんに話を聞いた。

Ingrid Fuzjko af. Georgii-Hemming◉日本人ピアニストの母と画家で建築家のスウェーデン人の父を持ち、ベルリンに生まれる。5歳の時、日本へ移住するが、父はスウェーデンに帰り、母子家庭で育つ。東京芸術大学を経て、NHK毎日コンクール賞など受賞。ウィーンでのコンサート直前に高熱をこじらせ耳が聴こえなくなるなど、幾多の波乱を乗り越え、プロデビュー。アルバム『奇蹟のカンパネラ』はクラシック界において異例の売り上げを記録。情感たっぷりの独特な演奏スタイルから絶大な人気を誇る、世界的ピアニスト©Samon Promotion, Inc.
|
リストを弾く時は大きな音でサーカス的に
母が弾いてくれたピアノが、私のピアノとの最初の出会いです。ただ、毎日、母からは「お前はバカだ」と言われ続けていたので、実は自分でも自分のことを〝イディオット〟だと、本気で思っていました。なので、ピアノを弾き始めて、周りの人たちから〝天才ピアニスト〟と呼ばれても、信じられませんでした。
子供の頃に聴いた曲で、印象に残っているのは、リストの「ラ・カンパネラ」。10歳の時に日比谷公会堂で(レオニード・)クロイツァー先生*が弾いたのを聴いて、「まあ! なんて美しい音色かしら」と感動したのを、今でも鮮明に覚えています。
それ以来、リストの曲が大好きになりました。リストの曲は、まるでサーカスのように人をびっくり仰天させるような旋律が多いんです。だから私もリストの曲を弾く時は、できるだけ大きな音を出して、サーカス的に弾くよう心がけています。
戦争が激化すると、ピアノを習うことも、演奏することもままならなくなりました。私は、人として1番醜いことは、誰かを傷つけることだと思います。命というのは自分のためにあるのではなく、〝愛〟を捧げるためにあるものです。その命を〝欲〟のために抹殺する、戦争をする人たちは、必ず地獄に落ちると思います。
命というと、私はネコが大好きで、捨てネコたちを何匹も拾って育てているの。ピアニストとして脚光を浴びる存在になれたのは、今まで私が命を救った動物たちが、恩返しをしてくれているからのような気がします。イヌは一生恩を忘れませんし、ネコは幸せを運んできてくれると、私は思います。
日本も戦争をして命を粗末にしたけれど、いい所もあり、悪い所もあります。ただ、昔の日本は、今よりもいろんな意味で美しかったと私は思うの。

©Ikuo Yamashita
|
恋はいい仕事をするための燃料
私がドイツに留学している間に、カラヤンを始め、多くの天才音楽家たちに出会いました。最高の音楽に触れられたこの時期の経験は、私のその後の音楽人生にどれだけプラスになったかわかりません。そのなかでも、1番の思い出となったのは、バーンスタインに出会ったことです。また20世紀最高の作曲家で指揮者のブルーノ・マデルナに認められ、彼のソリストとして契約したことは、私の人生の誇りのつとなりました。
最近、興味を持っている音楽家は何人かいますが、私はパリに住んでいますので、フランス人のローラン・コルシアというヴァイオリニストに注目しています。彼は私のパリ公演を聴きに来てくれましたが、とても素敵な方でした。
近年になって皆さんから、「魂のピアニスト」などと評されています。最近、高い技術を持った演奏家がたくさん出て来ています。ただ、テクニックというのは〝技巧的に早く正確に〟弾くということではないと思います。
私の演奏の中には詩や語りが入っていたり、さまざまな色彩を表現しています。作曲家がどういう想いでその曲を作ったかを、大切にしているつもり。だから、私の演奏は毎日変化します。本当のテクニックというのは、人の心に触れることができるかどうかではないでしょうか。私は、いいピアノの音色を出すには、恋愛が必要だと思いますよ。恋はいい仕事をするための燃料となるのよ。
私の今後の人生の目標、夢ですか? 私の夢は、有名になれなくてもいいから、私の音楽を聴いてくれる人の前でピアノを弾くことでした。これからもそうです。私にとって音楽、ピアノは、子供の頃から唯一諦めなかった夢です。私の演奏を聴いて癒される人がいる限り、私は演奏し続けます。
ロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴのファンの皆さん。当日は、どうぞ会場に足を運んでください。いい演奏をできるよう頑張ります。
*フジコさんの母のドイツ留学の時の恩師。フジコさんの才能を認めた最初の人物。
フジコ・ヘミング コンサート・インフォ
場所: Orange County Performing Arts Center
600 Town Center Dr., Costa Mesa
www.ocpac.org
■2007年2月13日(火)・8:00pm
♦チケット購入:$25~$85
OCPAC BOX OFFICE (☎714-556-2787)
All American Tickets (☎1-888-507-3287)
紀伊國屋書店 コスタメサ店 (☎714-662-2319)
ロサンゼルス店(☎213-687-4480)
三省堂書店コスタメサ店 (☎714-556-2200)
旭屋書店トーランス店 (☎310-375-3303)
H.I.S. (☎1-877-447-8721)
「魂のピアニスト」と称賛されるフジコ・ヘミングが、3年ぶりのアメリカツアーでロサンゼルスを訪れます。今回は、過去にエミー賞を受賞している南カリフォルニアの名門オーケストラ、グレンデール・シンフォニー・オーケストラとの共演で、演目はベートーベン・ピアノ協奏曲第5番変ホ長調「皇帝」。第2部には、カラヤンから「神様からの贈り物」と絶賛された韓国人ソプラノ歌手、スミ・ジョーが出演します。
(2007年2月1日号掲載)
フジコ・ヘミング◎リサイタル直後インタビュー
2009年7月24日、26日の2日間、The Broad Stage at Santa Monica College Performing Arts Centerにて、フジコ・ヘミングさんのソロピアノ・リサイタルを開催した。両日とも540席が完売。ベートーベンの『テンペスト』やショパンのエチュード、そしてトリにはフジコさんを一躍有名にしたリストの『ラ・カンパネラ』が演奏され、観客は一様に、情感あふれる、力強い演奏に感動した。最終日の終演直後に、フジコさんに話をうかがった。
フジコ・ヘミング(Ingrid Fuzjko Hemming)
日本人ピアニストの母と、スウェーデン人建築家の父の下、ベルリンで生まれる。10歳からレオニード・クロイツァーに師事。毎日コンクール入賞、文化放送音楽賞を受賞するなど注目を浴びる。28歳の時にベルリンへ留学。風邪による高熱で聴力を失い、スウェーデンへ移住。再びドイツへ戻り、音楽教師をしながら演奏活動を行う。1999年にNHKで放送されたドキュメンタリーをきっかけに大ブレイク。デビューアルバム『La Campanella』は200万枚を売り上げ、日本ゴールドディスク大賞を4度受賞。2008年にアメリカにて”Fuzjko Label”を設立、アメリカデビューを果たす。
私の公演は、いつもソールドアウトであってほしい
今回の公演を終えて、感想は?
今日は素晴らしい演奏ができました。自分の出来というのは自分にしかわからないものですが、すごくうれしいです。最近はすごく調子が上向きで、度胸も付いて、完全な演奏ができるようになりました。すごく満足しています。
この前ロスで弾いた時(2007年の公演)は、2千人か3千人くらい入る会場が完売になったんですが、ああいうのは向いていないかもしれません。私にはもっとこぢんまりした所が向いているし、お客さんが喜んでくれているのもわかるし。今回のような会場で2~3回演奏した方がいいです。お金のない苦学生とかを対象に、タダの演奏会をしたっていいわ。
今回のプログラムは、あんまり欲張って、色々とやらない方が良いと思ってレパートリーを決めました。ただ、『ハンガリアン・ラプソディー』は、今回弾くはずだったのだけど、ちょっと手を痛めて止めたんですよ。昨年12月にロンドンで、新しいフジコレーベルのCDを録音しました。そこはビートルズを育てた大物プロデューサーが作った素晴らしいスタジオで、「神の手」と言われるロンドンの技師たちが録音に携わってくださって。今までにないような音響のCDなので、皆さん興味を持っていただけると思います。
アンコールの2曲は、どちらもしっとりしていますが、何か意図はありましたか?
『ラ・カンパネラ』を弾いた後で、もう1回ブラボーが出るような曲を弾いてもしょうがないから、わざとしっとりした曲にしたの(笑)。お客さんが静かなのは感動と関係ないから。

|
今回も非常にパワフルな情感溢れる演奏でしたが、そのパワーの源はどこにありますか?
私は神様を信じているから、弾く時にはいつも「お守りください、お守りください」とお祈りしています。だから神様はちゃんと守ってくださるし、信仰は大切ですよね。
曲と曲の間で黙想しているのも、実は心配なんです。私、歳を取ってきているから、背中が丸くなっておばあさんみたいに見えないかしらと思って。カッコ悪いかなとか、そんなことばかり考えています(笑)。だから一所懸命、背筋を伸ばして。私の公演は、いつもソールドアウトであってほしいですから。もし将来聴く人がいなくなったら、ネコと犬のためだけに弾きますよ(笑)。
今回のお召し物は大変素敵ですね。いつもそのような装いで演奏されるんですか?
私のお世話をしてくれている友達が、京都などで芸者さんのお古などを探してくるんですよ。昔の着物の色って素晴らしいですからね。染め物も、私は好んでいます。海外で公演する時は、現地の方は絶対に着物がいいと言います。日本人はあまり喜びませんが(苦笑)。でも日本人、特に男の人はもっと着物を着てほしい。とても似合うから。
もうハッタリでは弾かない飾るから滑稽になる
ロサンゼルスの印象はいかがでしたか?
日本で言えば、軽井沢みたいにお洒落な街だし、歩いている人もお洒落な人が多いですね。私はアメリカ人が好きで、アメリカに憧れていました。だけども、昔は全然お金がなかったから。渡米しようと大使館に行っても、「いくらお金を持っているか?」と聞かれると、預金通帳も持ってなかった状態でしたので、仕方なくヨーロッパに留まったんです。
(指揮者の)小澤(征爾)さんにヨーロッパで会ったことがあるけど、モヤモヤしてたの。彼はそれでアメリカに来て、初めてパワーアップしたんですよね。アメリカ人てすごく寛大で、人間としては世界最高だと思います。
媚を売らないで、もっと純粋でありたい
フジコさんは、音楽を通して何を伝えたいですか?
さあ、何でしょうね。何で皆さんが私の演奏会に来るのかわかりません(笑)。ただ、ほかの演奏家からは、「フジコのピアノは深い」って言われたりします。きっと、信仰があるから深いんじゃない?深みとかは自然に出るもので、私は「作る」ことが全然できません。
この間、華道の大家の假かりやざき屋崎省吾さんの知り合いで、パリコレにも出たすごくきれいな女優さんがいて、彼女の首が痛くて回らなかったんですって。ところが私の演奏会に来て、「ラ・カンパネラ」を聴いたら、帰る時には首が治ってしまったと、私に言ってくれました。病院にいる人が私のCDを聴いたら、どういうわけか治っちゃったとか、そういう話をよく聞くから、どうもウソじゃないらしいわ。きっと私があまりにも神様に祈りながら弾いているから、それで効くのかな。薬みたいなものよね。
フジコさんにとってピアノや音楽とはどういうものですか?
私にとって、ピアノは人を慰めるものです。私も慰められているし、最近はお金も入って来るから、毎年、ユニセフにも寄付しています。(日本の自宅がある)下北沢辺りの野良ネコも助けることができました(笑)。すごくうれしい。
ピアノはお客さんが入る限りやりますよ。あとはネコと犬のためにね。ネコも結構、聴いているんですよ。人間と同じで、ネコにも色々いて、音楽なんか聴かずに尻尾巻いて逃げて行っちゃうのもいるしね(笑)。
今まではハッタリ。「こうやったらウケる」といったことばかりを考えていたけれど、バカバカしくなって。最近はいっぱいバッハを弾くようになりました。バッハなんてハッタリが利かないですからね。だから私は、媚を売らないでもっと純粋でありたいと思います。
東京では私のバッハをとても感激したとみんなが言ってくださったから、同じ曲をパリの友達のピアニストに「弾いてみな」と言ったの。そうしたら、まるでチョコレートみたいなバッハを弾いたから。飾るから滑稽になっちゃうのよね。
来年あたりから、全米ツアーもやる予定です。私、飛行機がダメなので、大きな車を借りてアメリカ横断するみたいだから、すごく楽しいと思います。やれるうちに早くやっておかないとね。
ロサンゼルス公演 演奏プログラム (2009年7月24日/26日)
DEBUSSY Clair de Lune(De “Suite Bergamasque”)
Jardin Sous la Pluie(“Estampes”)
BEETHOVEN Piano Sonata No. 17 in D Minor,Op. 31-2(Tempest)
CHOPIN Nocturne in E Flat Major, Op.9-2
Waltz in E Flat Major,Op.18-1(Grande Valse Brillante)
Étude in E Major, Op.10-3(Chanson de L’adieu)
Étude in G Flat Major, Op.10-5(Black Keys)
Étude in C Minor, Op.10-12(Revolutionary)
BACH Jesu, Joy of Man’s Desiring( Aria)
LISZT Un Sospiro(3 Études de Concert S144-3)
Frühlingsnacht(Schumann Transcription)
Grandes Études D’après Paganini No.6 S.141-6
La Campanella (Grandes Études D’après Paganini No.3 S.141-3)
Encore
CHOPIN Nocturne No.1 in B Flat Minor Op.9-1
J.M. Ravel Pavane pour une Infante Defaunte
(2009年8月16日号掲載)
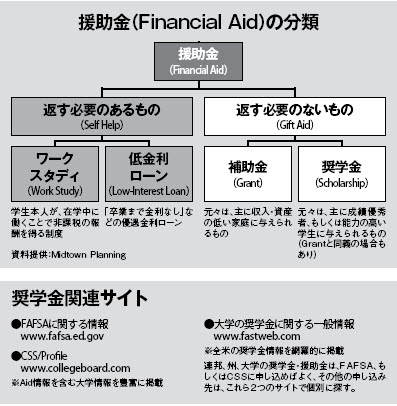





 ★★こんな人におすすめ★★
★★こんな人におすすめ★★ Tomasz Kolodziejak氏(新規事業開発ヴァイス・プレジデント)
Tomasz Kolodziejak氏(新規事業開発ヴァイス・プレジデント)