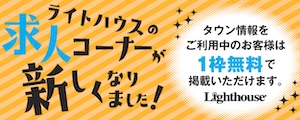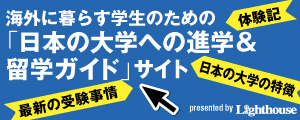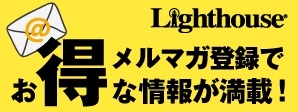『ラストサムライ』ではアカデミー助演男優賞ノミネート、続く『Memoirs of a Geisha』『バットマン・ビギンズ』『硫黄島からの手紙』では世界の名監督たちを魅了した。今や「ケン・ワタナベ」として圧倒的な存在感を誇る世界的スターだが、スクリーンを通して届けられる魂のメッセージの裏には、俳優として生き抜く覚悟と、それを支える人たちの姿があった。
「自分は何者なんだ」という信念を感じられれば、どこでもいい。

わたなべ・けん◉1959年、新潟県生まれ。日本国内、海外双方において、映画を中心にテレビドラマ、舞台と幅広く活躍する。『ラストサムライ』でアカデミー助演男優賞にノミネート、『バットマン・ビギンズ』『SAYURI』、現在公開中の『硫黄島からの手紙』他に出演。2006年に日本で公開した『明日の記憶』では、自らエグゼクティブ・プロデューサー、主演を務め、現在、北米公開に向けてプロモーション中。
|
表現する仕事がしたいと突き進んだ俳優の道
高校まではトランペットを習っていて、漠然とミュージシャンになれたらいいなと思っていました。でも、音楽学校はお金がかかるし、親父もリタイアしたので、無理かもしれないなと。受験勉強もしていたのですが、「表現する仕事がしたい」と思い、劇団のパンフレットを取り寄せました。
「大学と同じ4年間やってみて、どうしようもなければいいや」と思っていたら、入ってからの刺激がすごかった。演劇青年や音楽青年に囲まれて、「こいつらに追いつかないと」という気持ちで芝居や音楽に目覚めました。振り返ってみると、ずっとそう。「何かを高く望んで取り組む」というよりは、急に「何かをしたい」と思い立ち、ダーっと突き進んで、後から「ああ、枯渇していたんだな」と。理屈が先行しないんですよね(笑)。
劇団に入って2~3年経った25歳の頃に、「自分は楽しんでやっているのだろうか?」と疑問を持つようになりました。ひとつひとつの役を咀嚼した上で演じていたら、違うやり方があっただろうに、環境に流されているようで。ちょうどその時に、いい役をいただいたんです。精神的にも肉体的にも、後に残るものがあれば続けようと思わせてくれたのが、インカ帝国最後の皇帝を描いた『ピサロ』というお芝居でした。「俳優ってこんなに深いんだ」と目覚めましたね。
その後、前向きにやっていこうと、勢いに任せて突っ走り、仕事が増幅した時に、病気に見舞われました。まるで、F1のレースカーが全速力で走っている時に、「エンジンが止まったからリタイアして」と言われたようで、実感がなかったですね。その時は、周りに迷惑をかけて申し訳ないという気持ちばかりでした。しかし、後になって、大きなプロジェクトを断念せざるを得ないという無念の想いが押し寄せてきて、「こんなに悔しい気持ちを自分の中に閉じ込めていたのか」と驚きました。
初めての闘病生活では、生きるか、死ぬかで必死。克服を経て、2度目の発病の際には、「自分が社会で何かの役に立てるとしたら、演技しかない」「俳優として戻らないと、ある意味、生きている意味はない」と、強く思っていました。待っていてくださった関係者やファンの皆さんが、復帰した時に、心の底から喜んでくれたんです。それからは、出演する作品が社会にどのようにつながるのかということを、意識して仕事をするようになりました。
魂を揺らす仕事を探し巡り会った『ラストサムライ』
俳優の仕事は浮き草みたいな商売で、どこにでも流れて行けます。同時に、大きな役をやればやるほど、色が付いて狭くなってしまう。30代後半に自分の魂を揺らす仕事がないことに気づき始め、それまでのシリーズものをすべて辞め、小さくても新しい役や悪役などに取り組むようにしました。そうして2~3年経った時に、『ラストサムライ』のお話をいただいたのです。
アメリカの映画作りは、日本と違いスタート前はのんびりゆっくり。「本当にやるの?」という感じ。半年間、英語を勉強して、メーキャップテストや衣装合わせをして、スケジュールを空けて待っていたものの、キャンセルになったらどうしようと思っていましたね(笑)。
その代わり、始まる時は、いきなり始まる、急上昇のクランクインなんです。1シーンを1日で撮影するペースで、英語で芝居をすることもあり、緊張より集中のし過ぎで知恵熱が出ました。日本ではセリフの言い方で、何テイクも撮り直すことなどないんですが、発音が問題で「もう1回」の繰り返し。新人に戻ったような、久々の感覚が心地良かったですね。
『ラストサムライ』では、LAとニュージーランド、日本で8カ月撮影をしましたが、8カ月もやっていると、役を作る必要がないんです。毎日の生活の中で、朝起きて、朝食を食べて、メーク・衣装を終え、セットに着く頃には、そのままスーッと役に入っていける。自分が息をするように役と同化できる。役を作るというより、役を生きるという感覚。良くも悪くも俳優として確立してしまう40代に、そういう環境をもらえたということは贅沢な経験ですよね。
アメリカで仕事をしていたのは、このためだったのかと思いました。
ユニバーサルな『…Geisha』等身大の『明日の記憶』
『Memoirs of a Geisha(邦題:SAYURI)』では、ロブ・マーシャル監督が見ている世界はどこにあるのだろう、ということに集中していました。日本の描写はこうするべきだと、重箱に詰め込んでいくような概念を崩し、いろんな角度から見てもいいということを学ばせてくれた、ユニバーサルなチームでしたね。
その後、あまり自分と離れていない身の丈の人間を演じてみるべきだと思っていた頃、LAの書店で『明日の記憶』の原作と巡り会い、すごい勢いで読んだことを覚えています。自分が表現したいと思っていたことを気づかせくれましたね。プロデューサーには、「今までのイメージと全然違う」と心配されましたが、想いとしては火が点いていました。この映画に関しては、僕はプロデューサーではなく、監督や制作者、脚本家、最終的にはお客さんに作品を紹介する「イントロデューサー」だと思っています。
日本で映画化するにあたって、泣いておしまいという単純な「病気モノ」にはしたくなかったんです。自分が病気を経験したこともあり、そういう役をやりたくなかった。病気の人たちは日々、泣き暮らしているわけではなく、「それでも普通に暮らしたい」と思っていること、実際に病気を受け止めなければいけない人たちがいることを、僕たちがどう受け取るか、ということを伝えたかったんです。
現場の空気を焼き付け挑んだ『硫黄島からの手紙』
役作りのためには、資料ではわからない空気感を吸収するために、現場に足を運びます。『硫黄島からの手紙』でも、お墓参りを兼ねて、主役の栗林忠道(陸軍中将)が生まれ育った長野に足を運びました。山に囲まれて、雪の中で育った男が、海の中にポツンとある硫黄島で、どのように死を迎えたのか。何に喜び、悲しみ、苦しんだのか?彼の目線や住まいが脳裏に焼き付いて、演技をしながら「この景色、どこかで見たぞ!」と思いました。だから、実際の生存者の方々が映画を見て、「ここに私たちがいます」と言ってくれたのはうれしかったですね。
『硫黄島からの手紙』は、俳優として培った全精力を傾けないとできない仕事でした。政治的にも社会的にも影響力のある話で、ひとつ間違えると単なる愛国映画になってしまう。いろいろな意味で、慎重かつ大胆にしなければいけないと、イーストウッド監督とディスカッションをしながら進めました。
アメリカに留学したことのある男(栗林)を演じたのですが、日米で仕事をし、暮らして、友達ができて、それぞれのいい面を感じることが多くなった自分だからこそ、この役ができるんだな、3~4年アメリカで仕事をしていたのは、このためだったのかと思いました。
僕は、拠点というものは、特に意識していません。僕自身は一緒なのだから、生きていけて、「自分は何者なんだ」という信念を感じられれば、どこでもいい。LAは楽だけれど、新潟出身としては四季が恋しいですが……。一生懸命、自分の四季を呼び覚まさないとね。また、ここに暮らすようになって、大らかにタフになったと思います。「僕は僕で、こうやって生きています」というように、各々が許されていて、許容量が多い。
基本的には家族のいる場所が帰る場所です。そして1番大切なのは、子供にとってどこがベースになるかということ。「どんな仕事をしていきたい?」「子供にどんなアイデンティティーを持たせたい?」と、時間をかけ、ゆっくり考えていきたいですね。長いプロジェクトになるけれど、20~30年後に結果が出ればと思います。

The Last Samurai ©2003 Warner Bros.
|
最近の主な出演作品紹介
The Last Samurai[2003]
出演 | トム・クルーズ、渡辺謙、真田広之、他
監督 | エドワード・ズウィック
Memoirs of A Geisha[2005]
出演 | チャン・ツィイー、渡辺謙、コン・リー、他
監督 | ロブ・マーシャル
Memories of Tomorrow[2006]
出演 | 渡辺謙、樋口可南子、坂口憲ニ、他
監督 | 堤幸彦
Letters from Iwo Jima[公開中]
出演|渡辺謙、二宮和也、伊原剛志、他
監督|クリント・イーストウッド
(2007年1月1日号掲載)