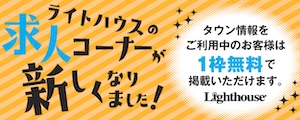(2021年9月1日号掲載)
独自の進化を遂げた日本のコンビニ

日本のコンビニについては、各国のメディアに加え、選手たちもSNSで情報を発信した。
|
今回の東京オリンピックでは、バブル方式といって選手団とメディア等の関係者は、選手村や指定されたホテルからの外出が制限され、一般の日本社会とは隔離された。そのため、海外の選手や関係者は選手村での食事の他は、レストランなどへの立ち入りは禁止されていた。その代わりに脚光を浴びたのが、日本のコンビニだ。
例えば、開会式の直前に東京入りしていたNBCのキャスター、サバナ・ガスリー氏は、ローソンの「からあげクン」と「たまごサンド」にハマって、毎日のように通い詰めたという。またニューヨーク・タイムスの記者は、同じ唐揚げでも砂肝を激賞していたし、選手たちの間では洗剤や下着などの日用品が調達できると喜ばれていた。
中国やアジアではこうした日本式のコンビニはすでに定着しているが、欧米の人々には改めて日本のコンビニは強い印象を与えたようである。そこで出てきたのが、日本式のコンビニを欧米にも欲しいという声だ。アメリカの選手や記者からもそうした意見が多く出ていた。多くの在米邦人や日系人がこれまで密かに抱いていた思いが、突然一般的になったというわけである。
実はコンビニの発祥の地はアメリカである。セブンイレブンはテキサスの氷屋が発展して食品や雑貨を扱うようになったものだ。日本のセブンイレブンは、この米国法人からライセンスを受ける形で1973年にスタートしている。当初は軽食としてブリトーを紹介したり、サングラスを売り物にしたりしていたが、やがて冬場に匂いも気にせずおでんを販売し始めた頃から日本化を加速させてビジネスとして成功した。2005年には、アメリカのセブンイレブンが日本のセブン&アイの傘下に入ることとなり、セブン&アイの米国法人という位置付けになっている。
一方で、発祥の地とはいえアメリカ社会におけるコンビニの地位は決して高くない。まず郊外型のコンビニは、高速のパーキングエリアやガソリンスタンドに併設されており、長距離の移動中にスナックや飲料を調達する、深夜や早朝にコーヒーや軽食を入手するといった限定的なニーズに対応したものだ。一方で、都市型のコンビニはタバコとロッタリー(宝くじ)の販売が中心というイメージがある。つまり、日本のコンビニと比較すると非常に狭いニーズに対応したニッチ・ビジネスとなっている。
日米のコンビニを取り巻く環境の違い
では、今回の五輪を契機として日本式のコンビニがアメリカでも流行するかというと、それは難しいだろう。まず、アメリカの場合、軽食の関係ではドライブスルーやデリバリーによるファストフード店の普及率が非常に高い中で、コンビニが対抗するのは難しい。また、各家庭の冷蔵庫が大きく食料品のストックが多いので「お腹が空いたらコンビニ」ではなく、冷蔵庫を開ければ済むという事情もある。単身世帯も同様だ。生活用品などについては、翌日配達などの通販が普及しているということもある。日本のコンビニで主要なビジネスとなっている公共料金の支払いやチケット販売などは、ほぼ100%インターネットでのサービスに移行しているのでリアルな店舗でのサービスは不要だ。
最大の理由は治安であり、アメリカではスーパーやファストフードの開いていない深夜の時間帯などは不要不急の外出をする習慣がない。そもそも深夜時間帯において、何かを購入するというコンビニエンス(利便性)が求められる局面が限られているのである。
そんなわけで、日本式のコンビニをアメリカに導入するのは難しそうだ。だが、今回の五輪で評判になった「唐揚げ」「カップ麺のバラエティー」「コンビニスイーツ」「コンビニアイス」などの商品カテゴリについては、米国市場でも十分にチャンスはあるということが分かった。コンビニという販路にこだわる必要はないと思うので、こうした日本発の夢のある軽食やスイーツが一気にアメリカでも普及し、定着することを期待したい。
|