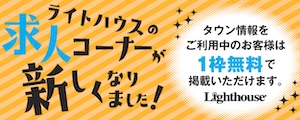(2023年11月号掲載)
デメリットがあれど、リモートを模索し続けるアメリカ

アメリカでも通常通りに出社する人は増え、再び渋滞が問題になる都市もある。
|
アメリカでは、コロナ禍後も日本で言うテレワーク、つまりリモート勤務が定着している。現在では100%リモートは少なくなり、全米平均では、週3日出勤で2日がリモートというのが「相場」のようだ。多くの経営者は、できればリモートを週1日としたいようだが、それでは優秀な人材は採用できないと言われている。それでも、2022年の春頃は「出勤2日、リモート3日」が相場だったのが、この1年で労働者側が1歩後退という感じだ。
アメリカの場合は、中級管理職以下は今でもリモート勤務を強く希望している。理由としては、コロナ禍の期間、100%リモート勤務を通じて獲得したワーク・ライフ・バランスを維持したいからだ。これに加えて、ニューヨークやサンフランシスコなど大都市圏の場合は、都市の治安が回復していない。それ以上に、多くの経営者も認めているのだが、日々のデイリー業務を回していくには、リモートの方が生産性が高いという声がある。
出勤すると、同僚同士の会話が増えるし、リアルな会議への参加などもある。その一方で、自宅で勤務する場合には邪魔が入らず集中しやすいので業務ははかどる。これは、コロナ禍の前から言われていたが、コロナ禍を通じて実証されたとも言える。
では、経営者の側はどうして社員を出勤させたいのかというと、具体的な理由がある。まず、開発や企画的な業務の場合は、リアルな雑談の中から新しいヒントが生まれることが多いという。リモートでは、日々の仕事に集中し過ぎて、アイデアの生産性は悪いというのだ。もっと切迫した理由があるのは、金融や法務の関係だ。特に相手と利害が対立する場合、本当にこの人物に融資をしていいのか、この人物の証言を信じて弁護していいのかといった際には、情報量の多い対面での会話の方がリスクを低減できるという。
別の意見としては、大学生の時から対面の会話の機会が少なかった新入社員は、正誤の間にあるグレーゾーンについて会話をするのが苦手であり、対面でコミュニケーションすることで、会話の実践を積むべきという声がある。もっと大局的には、通勤する人が増えないと、昼間人口が戻らないので、治安も都市経済もコロナ禍の以前の状態に戻らないという事情も都市によっては切実な問題となっている。
マニュアルのない日本の仕事
テレワークで生産性低下
アメリカでは、このような労働者と経営側の綱引きが当分続くであろうし、リモート勤務が全て否定されることはなさそうだ。その一方で、日本の状況は全く違う。現在でも一部のハイテク系や開発系、デザイン系の企業などではリモート勤務が週1〜2日の範囲で許されていることもある。だが、23年の秋の現時点では、多数の企業でほぼ100%出勤の体制に戻っている。
その理由は、アメリカとは全く違う。経営者、管理職から若手まで多くの日本の企業人が口をそろえて「テレワークでは生産性が上がらない」と言うのだ。企画とかアイデア、交渉時の相手の様子を判断、などという特別な問題ではなく、通常のデイリー業務に支障が出るというのだ。
例えば、経営陣は対面で報告を受けないと判断が難しいという。文書と資料だけでは判断できず、作業の中間報告を受けないと心配でならないらしい。また多くの管理職が、在宅勤務している部下が「勤務時間中にサボっていないか」を考えると心配でストレスが増すのだそうだ。若手は若手で、業務の知識をいちいち先輩に聞くのには、対面で相手の顔色をうかがってやらないと仕事が先へ進まないという。
要するに、日本の場合は仕事がマニュアル化されていない一方で、会社ごとに自己流で進めているため、職場の過去の経験値を伝承しないと仕事が回らない。加えて、個々人の職務範囲を厳密に決められないという問題もある。こうした問題の中にこそ、先進国中で最低だという日本の低生産性の理由があるのだが、多くの日本の企業や官庁は全く気付いていないようだ。
|