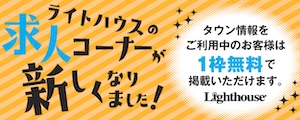家庭内問題における日米それぞれの警察の立場

児童相談所に警察官を置く自治体も増えている。
|
千葉県で 10歳の女児が実父から虐待を受けて殺されたニュースは、日本の社会に大きな衝撃を与えた。この事件では、亡くなった児童が虐待の事実を訴えたアンケートを教育委員会が父親に見せたことが、暴力をエスカレートさせたとして批判されている。
この問題だが、学校と教育委員会という教育現場と、児童相談所という福祉行政の機関だけでは、父親の暴力に対抗できなかったという見方がある。学校がアンケートを見せてしまったのは、父親に脅されたからだし、児童相談所も虐待を疑いながらも児童を家庭に戻してしまっているからだ。
こうした問題が起きるたびに、日本の場合は「親の権利」が強過ぎるという指摘がされている。そのために、児童相談所も学校も家庭内の問題に立ち入るのを躊躇してしまい、悲惨な事件を予防できないというのだ。
これに加えて、警察が関与できていない問題もある。アメリカの場合、子どもの生命を守るために警察が介入するのが当たり前だ。幼い子どもが一人で歩いているなど危険な状態を発見したら、目撃した第三者には警察に通報する義務を課している州も多いし、家庭内暴力は、重大な犯罪として位置付けられている。学校でも、親権のない親が子どもを連れ去ろうとした場合など、必要があれば警察の力を借りて子どもを保護することは当然とされる。
一方、日本では警察の立場は確立していない。まず、学校の場合だが、生徒による暴力については、できるだけ指導の延長で対処することとなり、よほど深刻な事例でないと警察の介入を要請することはない。保護者からの脅迫や恫喝なども同じだ。
また家庭内の場合はもっと難しく、監護権を主張する親と対決しながら警察が子どもを守るのは簡単ではない。そこには、警察はあくまで刑事事件の捜査のために存在しており、民事係争に介入できないルールが立ちはだかっている。ストーカー事件の防止がうまくいかないのもこのためだ。
警察の介入を阻む日本ならではのカルチャー
もちろん、今回の千葉県の事件でもそうだが、警察の力を導入しないと子どもの命が守れないという議論は活発化している。ストーカー事件も含めて、警察も「民事不介入の原則」をしゃくし定規に適用するのではなく、住民向け窓口の設置や内部研修の充実、実際に児童虐待の事件検挙は増加傾向にあるなど、社会の期待に応えようと懸命になっている。だが、その際に改めて障害となるのは、日本の社会全体にある警察に対する2つの偏見だ。
1つは、警察を過剰に恐れるというカルチャーだ。俗に「警察沙汰」という言葉があるように、日本の社会には、警察の捜査を受けたり、まして逮捕されたら大変だという心理が根強い。アメリカでは犯罪を犯した経歴、つまり犯罪歴が問題になることがあるが、日本の場合は逮捕歴が問題になるというように、とにかく警察は怖い、関わりたくないという心情がある。
もう1つは、その裏返しとしての警察不信だ。江戸時代以来の、お上は庶民の敵だというカルチャーが今でも残っており、警察官や警察組織が社会から正当な評価を与えられていない。例えば、テレビドラマでは、警察の組織は腐敗しており、正義の味方は出世コースから外れたアウトローの警部だけなどという設定が喜ばれるのも一例だろう。警察官によるスピード違反など不祥事があると、メディアは鬼の首でも取ったように大きく報道する。
こうした傾向の中で、例えば児童相談所が虐待事例を警察と共有しようとすると、社会的に「個人情報の漏えいだ」などと批判が起きてしまうのだ。
一時帰国した際、「日本の警察については、もう少しリスペクトしてあげていいのでは?」と意見を述べたこともあるが、「銃社会のアメリカで暮らして感覚がマヒしている」などと反論されることが多かった。しかし、一連の虐待やストーカー事件を受けて、日本の警察は変わろうとしている。その努力には注目していきたい。
|
(2019年3月1日号掲載)
※このページは「ライトハウス・ロサンゼルス版 2019年3月1日」号掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。